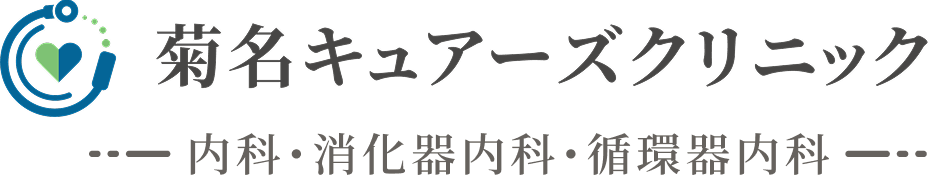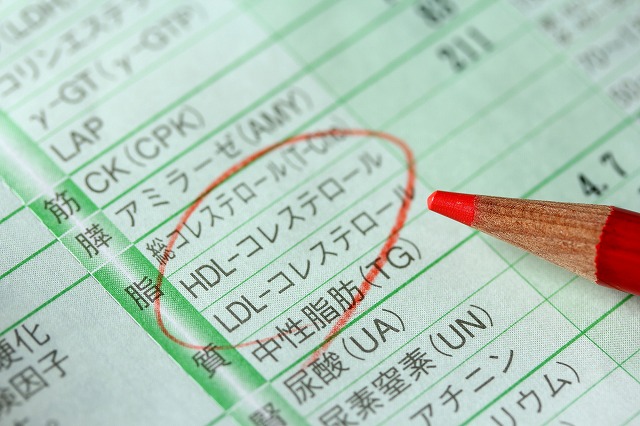 こんにちは。当院のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
こんにちは。当院のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
「健康診断でコレステロール値が高いと言われたけど、大丈夫?」
「脂質異常症って自覚症状がないって聞くけど、本当に治療が必要なの?」
「放っておくと動脈硬化になるって本当?」
脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が異常な値を示す状態のことを指し、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める「サイレントキラー(静かな病気)」と呼ばれています。
症状がないからと放置すると、気づかぬうちに血管のダメージが進行し、重大な病気を引き起こす可能性があります。
当院では、脂質異常症の診断から治療、生活習慣の見直しまで、患者さま一人ひとりに合った治療プランをご提案し、心血管疾患の予防に努めています。
また、「脂質異常症 食事」「脂質異常症 運動」「脂質異常症の治し方」「脂質異常症 薬 いつから?」など、ネットでよく検索される疑問にもわかりやすくお答えします。
このページでは、脂質異常症の種類・原因・診断・治療・合併症のリスク・日常生活での注意点 について詳しく解説します。
CARDIOLOGY-01脂質異常症とは?
脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)の値が正常範囲を超えている状態 を指します。
かつては「高脂血症」と呼ばれていましたが、現在では「脂質異常症」という名称が使われています。
脂質異常症は自覚症状がないまま進行し、放置すると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める ため、定期的な健康診断や血液検査が重要です。
CARDIOLOGY-02脂質異常症の種類と診断基準
脂質異常症は、以下の3つのタイプに分類されます。
LDL(悪玉)コレステロールが高い「高LDLコレステロール血症」
- LDLコレステロールが140mg/dL以上
- 血管の壁にコレステロールが蓄積し、動脈硬化を引き起こす
- 心筋梗塞・脳梗塞のリスクが上昇
HDL(善玉)コレステロールが低い「低HDLコレステロール血症」
- HDLコレステロールが40mg/dL未満
- LDLコレステロールを血管から回収する働きが弱くなる
- 動脈硬化が進行しやすい
中性脂肪が高い「高トリグリセライド血症」
- 中性脂肪が150mg/dL以上
- 肥満・糖尿病・脂肪肝と関連が深い
- 膵炎のリスクが高まることも
特に、LDLコレステロールが高く、HDLコレステロールが低い場合は、動脈硬化が進行しやすく、心血管疾患のリスクが高くなるため注意が必要です。
CARDIOLOGY-03脂質異常症の主な原因
生活習慣が大きく関与

- 脂質の多い食事(揚げ物・スナック菓子・加工食品など)
- 運動不足(脂質の代謝が低下)
- 肥満(特に内臓脂肪型肥満)
- 過度の飲酒(中性脂肪の増加)
- 喫煙(HDLコレステロールの低下)
遺伝的要因も関係
- 家族に脂質異常症や心血管疾患の人がいる場合は要注意
- 遺伝的にLDLコレステロールが高くなりやすい「家族性高コレステロール血症」
脂質異常症は生活習慣による影響が大きいですが、遺伝的な要因もあるため、家族歴がある方は特に注意が必要です。
CARDIOLOGY-04脂質異常症の検査方法
主な検査
- 血液検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)
- 動脈硬化のチェック(頸動脈エコー・脈波検査)
- 肝機能検査(脂肪肝の評価)
定期的な血液検査によって、脂質異常症の進行を防ぎ、動脈硬化のリスクを評価することができます。
CARDIOLOGY-05脂質異常症の治療方法
生活習慣の改善が基本

- 食事療法(動物性脂肪を減らし、魚・大豆製品・食物繊維を増やす)
- 適度な運動(ウォーキング・筋トレ)
- 禁煙・節酒(特に中性脂肪が高い場合)
薬物療法(必要に応じて)
- スタチン(LDLコレステロールを下げる)
- フィブラート(中性脂肪を下げる)
- エゼチミブ(コレステロールの吸収を抑える)
CARDIOLOGY-06放置すると怖い合併症
- 動脈硬化の進行
- 心筋梗塞・狭心症
- 脳梗塞
- 脂肪肝・膵炎
CARDIOLOGY-07まとめ
- 脂質異常症は自覚症状がないまま進行するため、早期発見・治療が重要
- 定期的な血液検査でコレステロールや中性脂肪をチェック
- 食事・運動・禁煙で血管の健康を守る
- 必要に応じて薬物療法を併用し、合併症を防ぐ