小児科は何歳まで受診できるのか
 一般的に、小児科の対象は15歳(中学3年生)までとされていますが、新生児や乳児をはじめ、幼児期、学童期、思春期の子供は、成長段階に応じた対応が必要です。さらに、成人では見られない疾患も存在しています。
一般的に、小児科の対象は15歳(中学3年生)までとされていますが、新生児や乳児をはじめ、幼児期、学童期、思春期の子供は、成長段階に応じた対応が必要です。さらに、成人では見られない疾患も存在しています。
小児科では、体のトラブルをはじめ、生活習慣、学習、発達、精神、性など幅広い面に対応するため、高校卒業あたりまではこれまでの成長経過を把握している小児科医へ相談するのがお勧めです。また、アレルギーや喘息、慢性的な神経疾患については、成人を迎えた後でもかかりつけだった小児科へ相談する方も多いです。
小児科では、各成長段階に適した診療や子供特有の疾患、心や発達に関するお悩みなど、包括的な治療が可能です。どんな些細なお悩みでも、お気軽にご相談ください。
また、当院では、一緒に受診される親御さんの風邪やアレルギー、予防接種などについても承りますので、気兼ねなくご相談ください。
小児科と内科の違いについて
同じ病気でも、大人と子供では、症状が異なることがあります。子供は症状を正確に伝えづらい場合もあります。
このため、小児科では、子供の成長や発達を踏まえて、1人ひとりの年齢に合わせて全身を丁寧に診察しています。
精密検査や専門的な治療が必要な場合は、連携医療機関をご紹介します。
小児科医は、地域の子供の主治医として、複数の専門科と連携することが必須です。同じ小児科でも、病院や医師によって得意とする分野が異なるため、お子さんに適した紹介先を見つけることが重要です。「どこに受診すればいいか分からない」場合でも、まずは小児科へお越しください。
小児のアレルギー疾患について
 アレルギー疾患は、年齢が進むにつれて、引き起こされやすいアレルギーが変化するという特性があります。
アレルギー疾患は、年齢が進むにつれて、引き起こされやすいアレルギーが変化するという特性があります。
アレルギーにかかりやすい要因を持つ患者様の多くは、乳幼児期の初めにアトピー性皮膚炎を発症し、その後、食物アレルギー、喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎などが次々に現れることが多いです。もちろん、全ての方がこのような流れを経験するとは限りません。
しかし、このように様々なアレルギー疾患を年齢とともに発症していく流れを「アレルギーマーチ」と言います。アレルギー疾患は全身を視野に入れて診断していく必要があるのです。
湿疹は皮膚科、鼻炎は耳鼻咽喉科と決めてしまうと、全身の状態を見落とし、適切な診断や治療が遅れてしまう可能性があります。まずは小児科で全身の状態を確かめ、その後、各専門科へ受診するかどうかを判断することが重要でしょう。
子どもの年齢に応じて気を付けた方がいい症状・病気
乳児期早期
生後3ヶ月頃までは、風邪を引くことはあるものの、発熱する傾向は少ないです。
もし発熱の症状が見られる場合、重症な細菌感染症などを検討する必要があります。
乳児期
食物アレルギーを発症する年齢です。食物の原因を血液検査だけで特定するのは難しく、疑わしい食品を避けるといった対策だけでは不十分です。正確な診断と迅速な対応が、将来の健康な成長に繋がります。
乳児期・幼児期
多種多様な風邪ウイルスに感染し、免疫を身につける大切な時期です。
RSウイルス、溶連菌、アデノウイルス、インフルエンザウイルス、手足口病など、子供たちがかかりやすい感染症は沢山存在しています。
これらの病原菌の中には、迅速検査で簡単に診断できるものもあります。
さらに、発熱に伴い、熱性けいれんを起こすケースもあります。風邪やアトピー性皮膚炎、喘息、花粉症などのアレルギー性疾患にかかるお子さんも少なくありません。
学童期
多くの風邪ウイルスに対する免疫を得ており、発熱や病院へ受診する回数も少しずつ減っていきます。
一方で、肥満、低身長、おねしょ、学習の困難など、幼児期には目立たなかったトラブルを抱えている可能性もあります。
思春期
慢性頭痛や起立性調節障害などの自律神経症状、生活習慣の乱れ、二次性徴のトラブル、心理的な異常など、多様かつ複雑な症状や悩みが現れることがあります。
子供の心理的トラブル
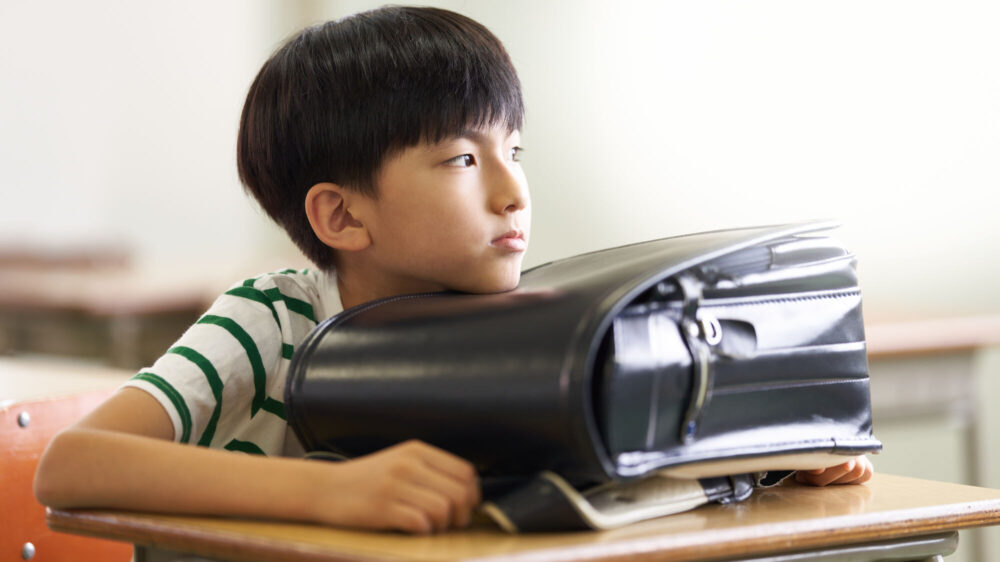 お子さんが小児期や思春期に心理的な問題に直面した際、どこでアドバイスを求めるかについて迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お子さんが小児期や思春期に心理的な問題に直面した際、どこでアドバイスを求めるかについて迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こういった診療を受け付けている医療施設はあまりないため、最初に小児科にご相談いただくのが適切でしょう。
実際、身体的疾患によって起こっている可能性もあります。全身を包括的に診察するためにも、まずは小児科へご相談ください。
成人でも小児科へ行けるのか
保護者の方で風邪や鼻炎、花粉症などに対する薬の処方、予防接種を希望していましたら、お気軽にご相談ください。
受診時に持って行った方がいいもの
症状が始まった際の記録や、熱の変化の表などをとっておくと、診察時にかなり役立ちます。発疹の様子や、便の色や状態が気になる場合は、写真を撮って保存しましょう。
けいれんや子どもの心配な症状や仕草については、動画でも記録しておくと良いでしょう。
小児科を受診する際は、母子手帳とお薬手帳を必ず持って受診してください。

